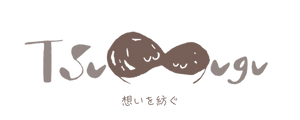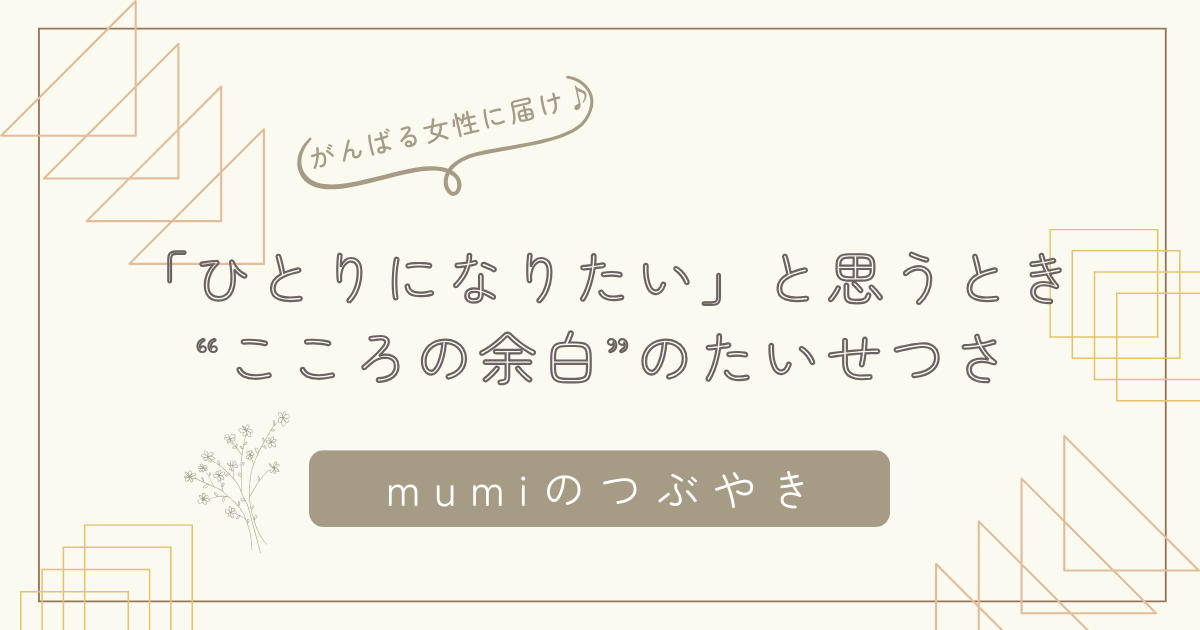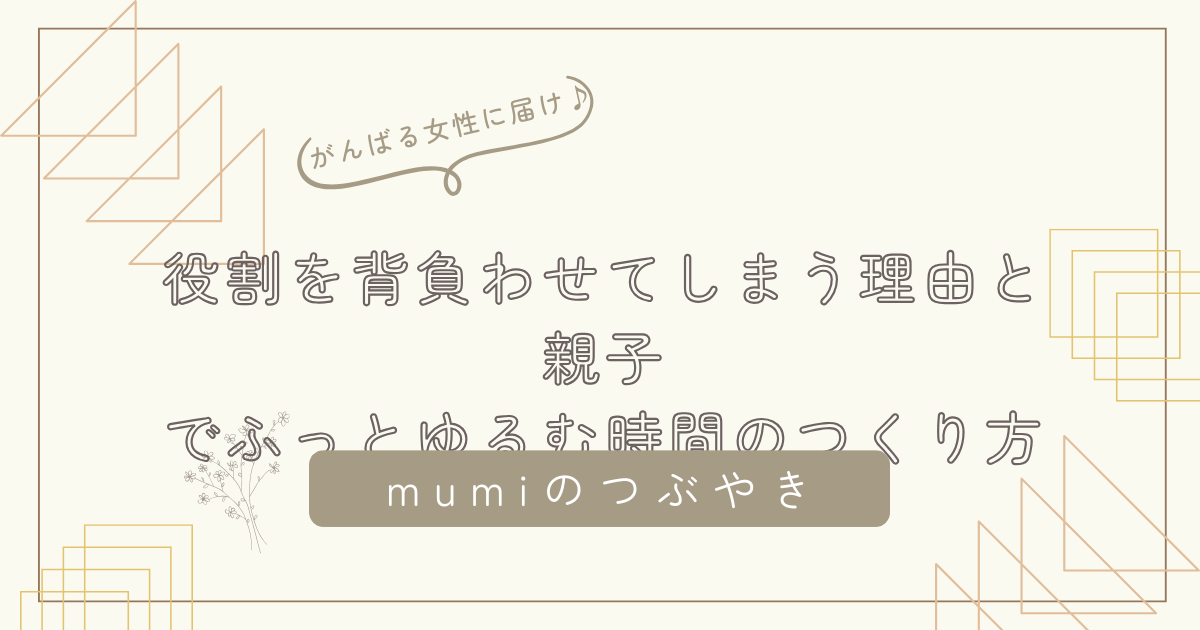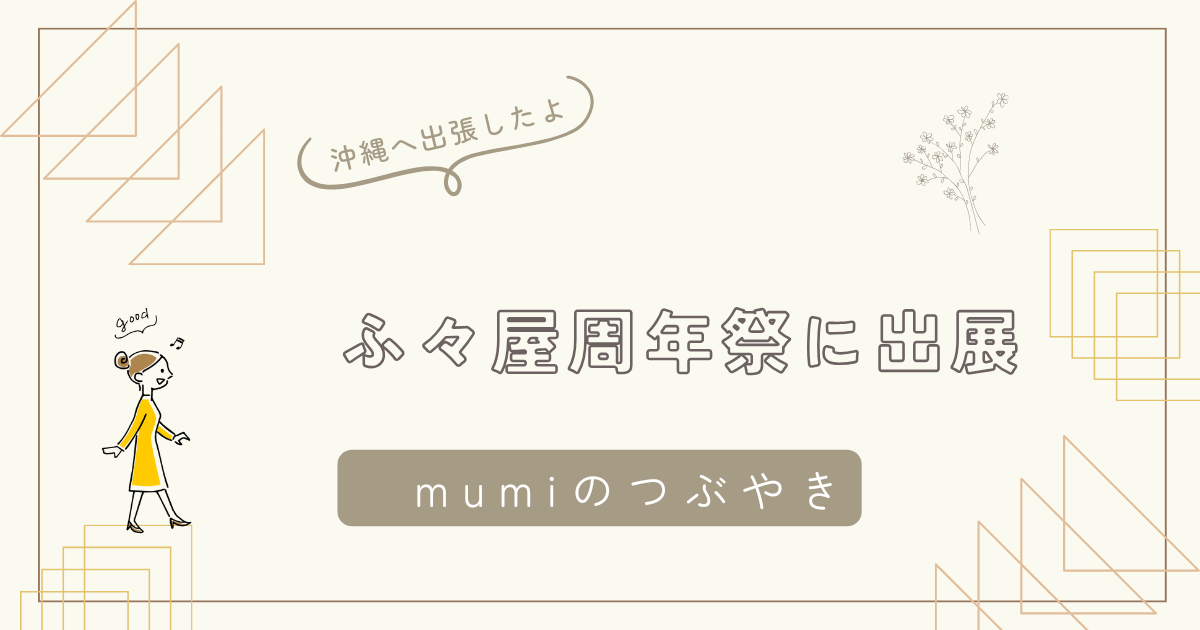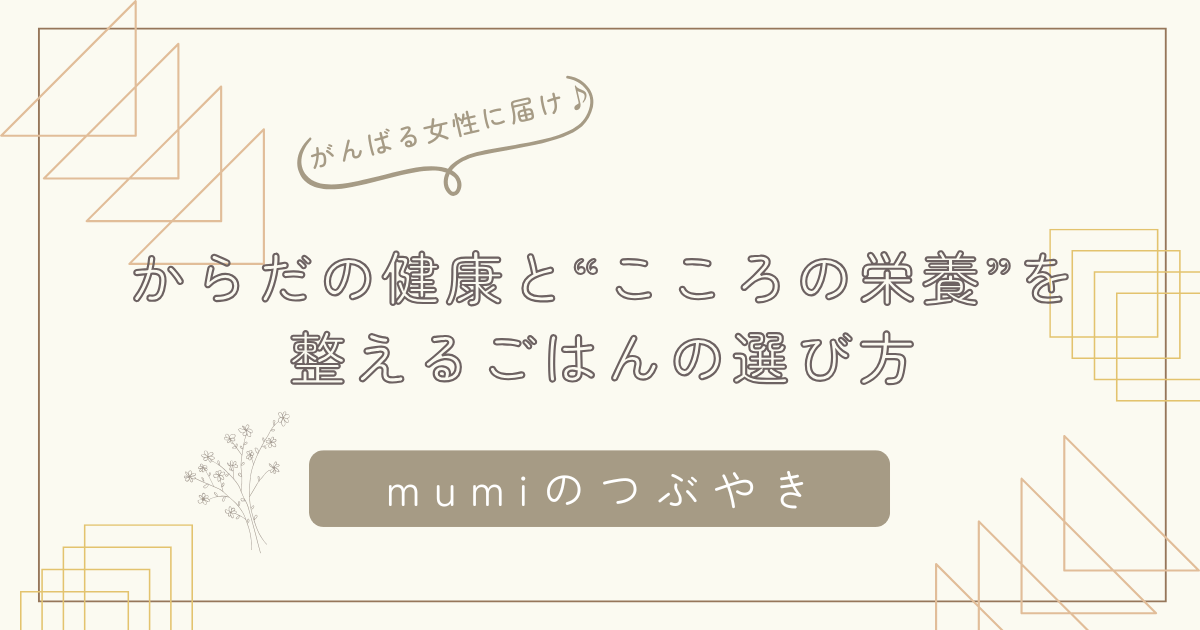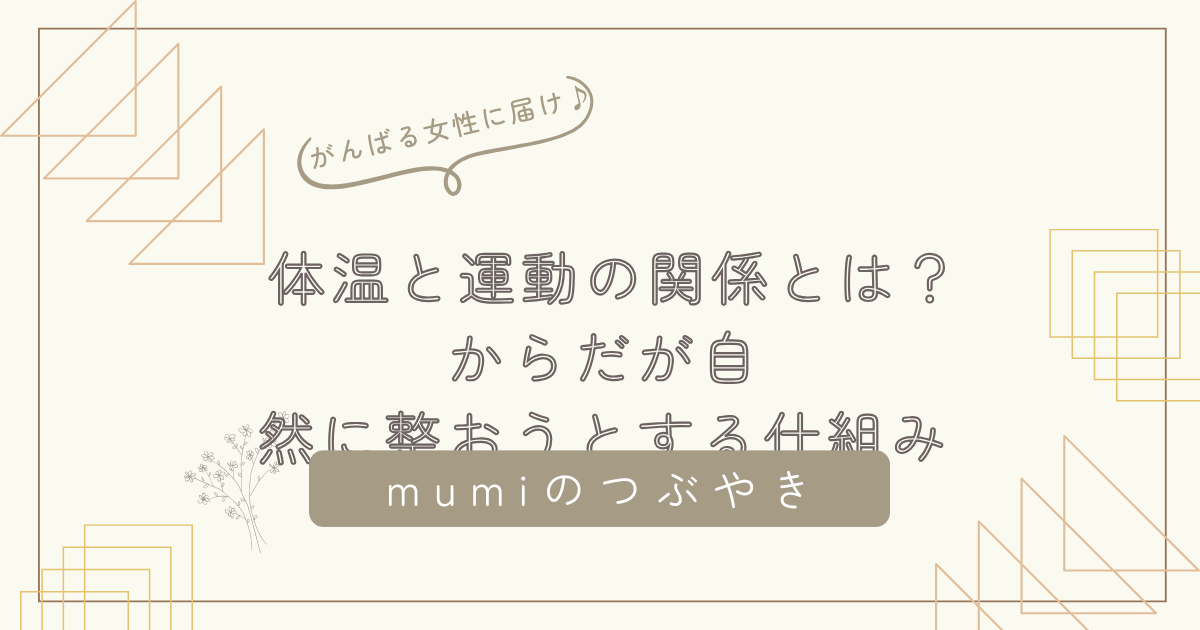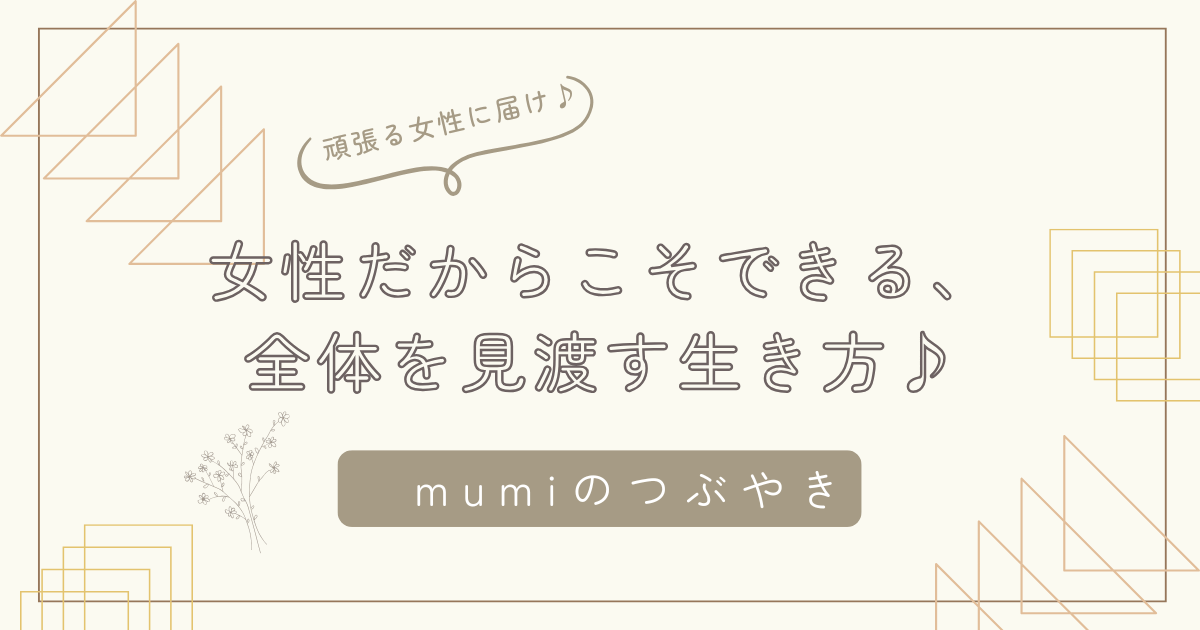不登校は“親のせい”じゃない。こどもの特性と心のサインを受けとめるために大切なこと/石狩
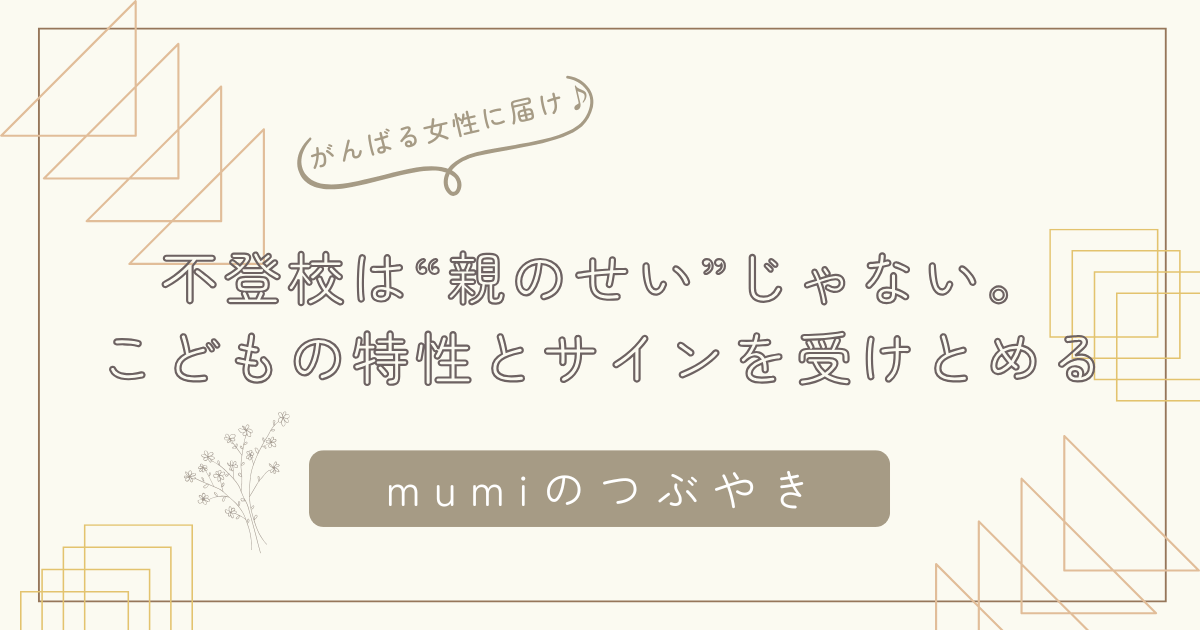
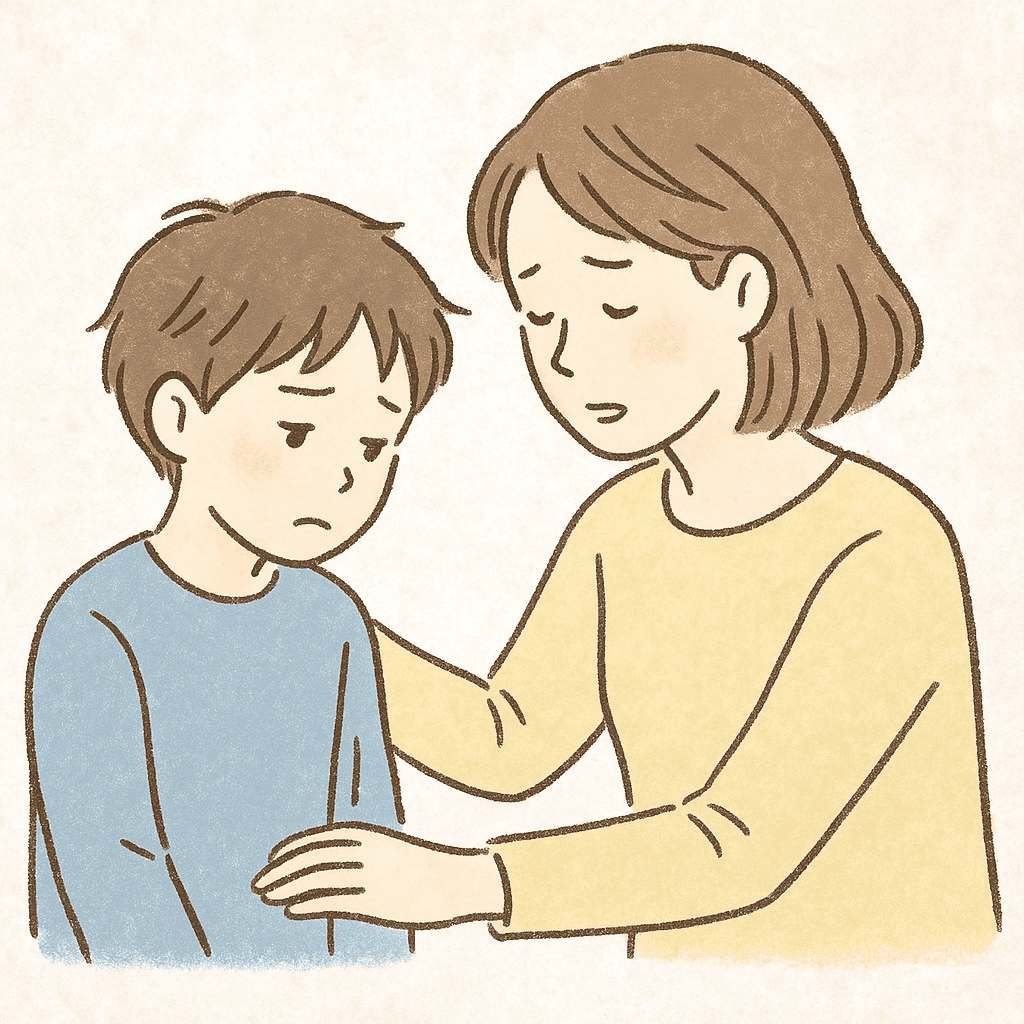
「こどもが学校に行けない」その現実にゆれる、親のこころ
こどもが学校に行けない。
そんな現実に直面したとき、親のこころは大きく揺れますよね。
「どうしてうちの子だけ…?」
「わたしの育て方が悪かったのかな」
そうやって、自分を責めてしまう気持ち。
その優しさこそ、あなたがどれだけこどもを想っているかの証です。
でも、こどもが学校に行けないのは“あなたのせい”ではないんです。
不登校の背景には「からだの特性」や「感覚の敏感さ」があることも
最近の研究では、発達や感覚の特性が不登校に関係していることも分かってきています。
たとえば、
・板書が苦手
・まわりの音が気になって集中できない
・椅子に座っているのがしんどい
こうした“ちょっとした苦手”の背景には、実は「あかちゃんの頃に残った原始反射(げんしはんしゃ)」が関係していることもあります。
原始反射とは、生まれたばかりの赤ちゃんがもっている“本能的な反応”のこと。
本来は成長とともに自然と消えていくものですが、何らかの理由で残ってしまうと、姿勢のバランスや感覚の処理に影響が出てしまうんです。
その結果、こどもは“じっと座る”“音を我慢する”“みんなと同じ行動をとる”ことに疲れてしまい、からだが“これ以上がんばれない”とストップをかけるように、学校に行けなくなることがあります。
「どうしてできないの?」の前に、「どうしてつらいのかな?」と聴いてみよう
不登校のこどもは、“行きたくない”のではなく、“行けないほど疲れている”こともあります。
まわりの大人は「どうすれば学校に行けるか」を考えがちですが、いちばん必要なのは、“安心してやすむ時間”。
こどもが自分のペースを取り戻すためには、
「がんばらなくてもいいよ」
「ここにいていいよ」
というメッセージが必要なのかもしれません🌿
あなたが整うと、こどもも整う——それは“生理的共鳴”という力
ここでたいせつなのが、あなた自身のこころとからだの状態。
実は、自律神経のリズムや呼吸のテンポは、“共鳴”すると言われています。
あなたが焦っていると、こどもも緊張し、あなたが深く息をしていると、こどもの呼吸もゆっくりになる。
これは「生理的同調」と呼ばれる現象で、あなたの安心が、そのままこどもの安心につながるという研究結果もあります🕊️
だから、こどもを変えるより、まずはあなた自身をゆるめることが、いちばんのサポートなのかもしれない。
今日からできる、親子の“整う習慣”
☑ 朝、こどもの前で深呼吸をしてみる
☑ 朝起きたらカーテンを開けて、日の光を浴びる
☑ 一日の流れの時間をルーティンにする
☑ 無理に笑わず、素直な気持ちを伝える
そんなちいさなことの積み重ねが、親子のこころをやさしく整えてくれます🌿
「こどもを変える前に、まずは自分をゆるめてみる」
不登校のこどもを支えるには、あなたが“自分を責めない”ことがいちばんたいせつです。
こどもが笑えるようになる前に、まずあなたが深く息をして、こころの余白を取り戻すこと。
あなたが整えば、その穏やかさが、波紋のようにこどものこころにも届いていきます🍃
焦らなくていい。
完璧じゃなくていい。
「こどもを変える前に、まずは自分をゆるめてみる」
それが、いちばんやさしいはじまりなのかもしれません🌸
さいごまでお読みいただき、ありがとうございます。